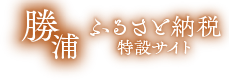本文
伝統を受け継ぎ、ていねいな酒造りを続ける吉野酒造

腰古井 推奨720ミリリットル、腰古井 大吟醸1800ミリリットル(写真は720ミリリットル)/腰古井 純米大吟醸仕込梅酒 500ミリリットル
老舗酒造が昔ながらの手法で作り続ける、「腰古井(こしごい)」のラインナップ。ふるさと納税返礼品には、単品のほか数種類をセットにしたものなどがあります。
代々受け継がれる老舗の日本酒
200年近く続く吉野酒造、現在は14代目の吉野慎一さんが受け継いでいます。敷地内には、切妻屋根が連なる酒蔵、レンガ造りの煙突、醸造の神様をお祀りする松尾神社など、歴史を感じさせる重厚な建物が並び、そのほとんどは国の登録有形文化財に指定されています。代表銘柄の「腰古井」は、周辺の地名である腰越(こしごえ)が由来。この「越」を古い井戸の「古井」をあてて命名したといいます。
酒づくりのモットーは「素材を大切に、昔ながらの手法を守り続ける」こと。手間を惜しまず、時間を惜しまずに醸す日本酒は、お酒の鑑評会などで数々の賞を受賞しています。



水や精米へのこだわり
こだわりの酒造りに使われる仕込み水は、敷地内の横井戸へと山から引いた自然水。このやわらかな軟水を使うことで、女酒とたとえられる口当たりのやさしい日本酒ができあがります。原料となる米も自社で精米。1回の精米量は約1200kg、普通酒で約8時間かけて70%に、吟醸クラスはさらにその倍以上の時間をかけて60%以下に磨きあげるといいます。この工程で大切なことは、米の摩擦熱による砕米やひび割れを抑えつつ、米の粒を揃え、雑味の原因となる糠が残らないように磨くこと。次の工程の洗米、浸漬(しんせき)において、米の水分量にバラツキが生じると、蒸し上がりや製麹、発酵にも影響を及ぼすからです。こうしてていねいに精米された米は様々な工程で手をかけ醸造され搾られたのち、澱引き、濾過、火入れ後にタンクへ貯蔵。さらに瓶詰前の濾過で味のバランスを整え、熱殺菌処理を行って品質を安定させるなど気の遠くなるような工程を経て、やっと日本酒が完成します。



新たな試みで梅酒が誕生
日本酒のみ造り続けてきた吉野酒造に、平成21年(2009)、新たに梅酒が仲間入りをしました。きっかけは、地元農業者の高齢化により、放置されている梅の木が増えていると知ったこと。この梅の実を有効活用できないかと考え、日本酒ベースの梅酒作りをスタートさせました。いろいろな日本酒をベースに試行錯誤を繰り返した結果、相性の良かった純米大吟醸仕込みの高級感あふれる梅酒が誕生。その後、お客様の要望に応えるかたちで、辛口タイプの吟醸酒で仕込んだ、さっぱり味の梅酒が加わりました。材料は梅の実と氷砂糖、自社の日本酒のみ。無添加ならではの自然な味と香り、上品な甘みが好評で、定番の人気商品になったといいます。

「和醸良酒」の精神で真摯な酒づくり
吉野酒造では、代々南部杜氏の酒造りを受け継いでいます。蔵人がよく口にする「和醸良酒(わじょうりょうしゅ)」、これは酒造りに関わる人々のチームワーク(和)によって良い酒が生まれるという意味。複雑な酒づくりの工程で、日々の変化に対応しながら、蔵人全員が力を合わせてひとつの味をつくりあげることの大切さ、大変さを表しています。昔ながらの手法を守りながら、「和で醸す」吉野酒造のお酒をぜひ、味わってみてください。

ほかにこちらの商品もおすすめ!

腰古井 純米大吟醸 吟の舞ソフト 720ミリリットル