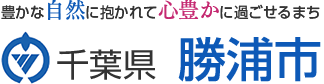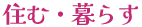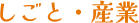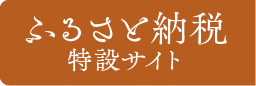本文
障害者福祉(手帳・サービス・手当等)
ページ内リンク
身体障害者手帳
対象者
身体に一定以上の障害のある方。
『視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・肢体(上肢・下肢・体幹)・心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓』
内容
各種の援護を受けるために必要となる手帳です。
障害の程度は、1級(重度)~6級までの6段階です。
※申請には次のものが必要です。
- 診断書(福祉課に用意してあります)
- 印鑑
- 写真1枚(たて4cm・よこ3cm)
療育手帳
対象者
児童相談所(18歳未満)または、障害者相談センター(18歳以上)において、知的障害と判断された方。
内容
各種の援護を受けるために必要となる手帳です。
障害の程度は、○A(最重度)~Bの2(軽度)までです。
※交付を受けるためには福祉課へ申請して下さい。
精神障害者保健福祉手帳
対象者
精神の障害により、日常生活や社会生活に支障がある方。
内容
税制上の優遇措置などがあります。
障害の程度は、1級~3級までの3段階です。
特別児童扶養手当(支給月:4月・8月・11月)
対象者
20歳未満で、心身に障害のある児童を扶養している父母または養育者の方。
※所得制限があります。
障害等級表はこちら[PDFファイル/142KB]
政令で定める特別児童扶養手当における障害基準一覧はこちら[PDFファイル/118KB]
障害児福祉手当(支給月:2月・5月・8月・11月)
対象者
精神または身体に重度の障害を有するために、日常生活において常時の介護を要する20歳未満の方。
※所得制限があります。
心身障害者福祉手当(支給月:4月・10月)
対象者
身体障害者手帳(1級・2級)、または療育手帳(○A・Aの1・Aの2・Bの1)を持っている20歳未満の方を扶養している保護者。
※障害児福祉手当を受給している場合は除かれます。
特別障害者手当(支給月:2月・5月・8月・11月)
対象者
精神または身体に著しい重度の障害を有するために、日常生活において常時特別の介護を要する20歳以上の方。
※所得制限があります。
ねたきり身体障害者福祉手当(支給月:4月・10月)
対象者
居宅において、おおむね6ヵ月以上ねたきりで、入浴・食事・排便などの日常生活に介護を要する18歳以上65歳未満の方を介護している方。
※特別障害者手当などを受給している方除かれます。
在宅重度知的障害者福祉手当(支給月:4月・10月)
対象者
療育手帳の程度が、○Aの1・○Aの2・Aの1・Aの2と判定された20歳以上の方を介護する方。
※特別障害者手当などを受給している方は除かれます。
小高御代福祉手当
対象者
当該年度において、新たに身体障害者手帳または療育手帳を取得した方。
石井久雄福祉手当(支給月:3月)
対象者
身体障害者手帳(1級・2級)または療育手帳(○A・Aの1・Aの2)を持っている18歳未満の児童を扶養している保護者。
交通事故により父母または父母の一方と死別した、義務教育終了前の児童を扶養している方。
心身障害者扶養年金
対象者
身体障害者手帳(1級~3級)・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)を所持している方などを扶養している65歳未満の家族の方。
内容
心身に障害があるため、独立自活することが困難な方を扶養している方が、その生存中毎月一定の掛金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された心身障害児(者)に終身一定の年金を支給する制度です。
※掛金は加入時の年齢によって異なります。
重度心身障害者医療費支給事業
対象者
身体障害者手帳(1級・2級)、療育手帳(○A・○Aの1・○Aの2・Aの1・Aの2)、精神障害者保健福祉手帳(1級)を所持している方。(65歳以上で新たに助成対象者となる障害者手帳が交付された方は対象外となります。)
内容
医療保険を利用し、診療や投薬等を受けた場合の医療費を助成する制度です。医療保険外の費用や、高額療養費、付加給付等として償還される分は助成対象外です。
自己負担額として通院1回、入院1日につき300円を負担いただきます。(市町村民税所得割非課税世帯については無料です。)
精神障害者医療費支給事業
対象者
低所得世帯で、「精神保健及び精神障害者福祉法」第5条の規定による精神病者・知的障害および精神病質者で、6ヵ月以上継続して入院している方。(ただし、重度心身障害者医療費の受給者は対象となりません。)
内容
保険医療機関で診療を受けた方が、その自己負担の中から保険で支給される額を控除した金額の2分の1を支給します。
※所得税非課税に限ります。
理容サービス事業
対象者
居宅において、おおむね6ヵ月以上ねたきりで、入浴・食事・排便などの日常生活に介護を必要とする18歳以上65歳未満の方。
内容
市が委託した理容業者により、訪問による散髪・顔そりを受けることができます。
※最大年6回分を限度として、無料理容サービス券を交付します。
自立支援医療の給付について
育成医療
対象者
18歳未満の身体に障害のある児童、または治療を行わないと将来障害を残すと認められる疾患のある児童。
内容
治療によって確実な治療効果が期待できると認められる指定自立支援医療機関での治療に対し、その費用の一部を公費で負担し、自己負担額が保険診療費の1割負担となります。また所得に応じ自己負担限度額が設定されます。
更生医療
対象者
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方。
内容
障害の程度を軽くし、または障害の進行を防ぐための医療に対し、その費用の一部を公費で負担し、自己負担額が保険診療費の1割負担となります。また所得に応じ自己負担限度額が設定されます。
精神通院
対象者
精神疾患のため外来で治療を受けている方。
内容
精神障害の治療で通院した場合の医療費に対し、その費用の一部を公費で負担し、自己負担額が保険診療費の1割負担となります。また所得に応じ自己負担限度額が設定されます。
補装具費支給事業
対象者
身体障害者手帳の交付を受けた方。(障害者相談センターの判定が必要な場合もあります)
内容
職業、その他日常生活の能率的向上を図るため、補装具の交付と修理に係る費用を支給します。
補装具の種目
車いす・座位保持装置・義肢・装具・補聴器・盲人安全杖など
※所得に応じて自己負担があります。
日常生活用具給付事業
対象者
身体障害者手帳を所持する方。(障害程度により給付品目が決められています)
内容
特殊寝台・盲人用時計・特殊マット・入浴担架・透析液加温器・ストマ装具・住宅改修などの給付を行います。
※所得に応じて自己負担があります。
福祉タクシー事業
対象者
身体障害者手帳(1級・2級)または療育手帳を所持している方。
内容
タクシー料金を支払う際、手帳を提示し、市が交付する「福祉タクシー利用券」を1枚渡すことにより500円までが差し引かれます。
※利用券(46枚綴)を交付します。タクシー1回の利用につき、最大2枚の利用券が使えます。
入湯料助成事業
対象者
身体障害者手帳を所持している方。
内容
年10回を限度として利用できる券を交付します。
利用できる施設・・・勝浦温泉・三日月シーパークホテル勝浦内 アクアパレス・松の湯
かつうら海中公園滞在型観光施設eden内スパ施設
障害福祉サービス
障害の種別(身体・知的・精神)にかかわらず、障害のある方々、難病を患っている方々が必要とするサービスを利用できるように、その仕組みを一元化して施設や事業を再編しました。
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
|---|---|
| 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
| 同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等を行います。 |
| 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動、または生産活動の機会を提供します。 |
| 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
| 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活、または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
|---|---|
| 宿泊型自立訓練 | 知的障害又は精神障害を有する障害者について、居室その他の設備を利用し、宿泊をしながら日常の生活能力向上や相談等必要な支援を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型) |
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
| 移動支援 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します。 |
|---|---|
| 地域活動支援センター | 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流などを行う施設です。 |
| 日中一時支援 | 障害者等の日中における生活の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等の日常的に介護している家族の一時的な休息や放課後ケアを行います。 |
| 意思疎通支援 | 聴覚、言語機能、音声機能等の障害のため意思疎通を図ることに支障がある方に、手話通訳者等を派遣し意思疎通の円滑化を支援します。 |
| 福祉ホーム | 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室などを提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 |
| 児童発達支援 | 通所による、障害児に対しての日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を提供します。 |
|---|---|
| 放課後等デイサービス | 学校就学中の障害児に対して放課後や夏休み等の長期休暇において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 |
| 保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援をします。 |