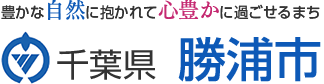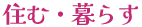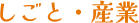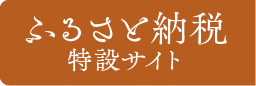本文
「望まない受動喫煙」をなくします
健康増進法が平成30年7月25日改正され、令和元年7月1日より施行されました。
この改正により多数の人が利用する施設(公共機関、飲食店、事業所等)では受動喫煙を防止する措置をとる必要があります。
健康増進法が改正されました
「健康増進法」は国民の健康増進の総合的な推進を目的として平成14年8月2日に公布されました。
その中で「受動喫煙」に関する規定は、多数の人が利用する施設における対策は努力義務でした。
その後の研究で「受動喫煙」による健康への影響が「肺がん」「脳卒中」「虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞など)」「乳幼児突然死症候群(何の予兆・既往歴がない乳幼児が突然死に至る原因不明な病気)」の発症について、因果関係を推定するに科学的根拠は十分と評価されたことから「望まない受動喫煙をなくす」ため、今回「健康増進法」が改正され、受動喫煙対策について罰則規定のある実施義務となりました。
改正の趣旨
- 喫煙者が一定数いること、受動喫煙の健康への影響を踏まえ「望まない受動喫煙をなくす」ことを目的とする。
- 健康への影響が特に大きい20歳未満のこども、疾患を抱える人が主な利用者となる施設などで受動喫煙対策を徹底する。
- 受動喫煙対策を実施する施設等について、その種類・場所、利用者の違いによって受動喫煙防止の対策を義務付けする。
改正の概要
国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努める。
国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権限者その他関係者は、受動喫煙が生じないよう、防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努める。
国は受動喫煙防止に関する施策の策定、必要な調査研究を推進するよう努める。
多数の人が利用する施設で喫煙が禁止されます
多数の人が利用する施設の種類に応じて、一定の場所以外の喫煙が禁止されます。
第一種施設 令和元年7月1日施行
学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎 → 原則敷地内禁煙
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に喫煙所を設置することができます。
※勝浦市役所については、法施行に先立ち4月1日より敷地内禁煙となっています。
第二種施設 令和2年4月1日施行
上記以外での多数の人が利用する施設 → 原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可能)
事務所、工場、ホテル・旅館(ロビー、エントランスなど)、飲食店
※喫煙専用室内では飲食はできません。
※旅館・ホテルの客室などは対象外となります。ただし、喫煙をする場合は受動喫煙を生じさせないよう周囲に配慮が必要です。
既存の経営規模が小さな飲食店について
既に開店・営業している個人または中小企業が経営している客席面積が100平方メートル以下の飲食店については、喫煙専用の部屋、場所の設置を求めることが経営に影響を与えることが考えられることから、一定の猶予措置(特例措置)が与えられます。
特例措置については、経営規模(資本金)及び面積(厨房、倉庫などを除く)を要件として判断します。
「受動喫煙」とは
タバコの煙は、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」、火のついたタバコの先から立ち上る「副流煙」、喫煙者が吸い込み吐き出した「呼出煙」と分けられます。副流煙には主流煙と同じく体に有害な成分が含まれていて、ニコチン、タール、一酸化炭素などの成分量は主流煙よりも多いといわれています。また「呼出煙」は一旦喫煙者の体内に入りますが吐き出した煙・呼気にも有害な成分が残っています。
この副流煙や呼出煙を自分の意思とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」といいます。
室内はもとより、室外においても風向きなどによっては「受動喫煙」被害を受ける場合があります。
受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすことがわかっています。
ちなみに喫煙者自身も「受動喫煙」になり得ます。
喫煙所で喫煙をした場合、自ら吸っているタバコの「主流煙」の他、自分のタバコからの「副流煙」、他の喫煙者からの「副流煙」「呼出煙」にさらされており、喫煙している以上のリスクがあることを理解してください。
厚生労働省 受動喫煙対策ホームページ<外部リンク>