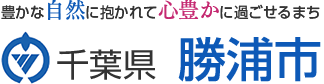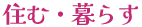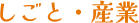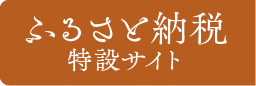本文
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
老齢年金生活者支援給付金
支給要件(以下の全てを満たす方)
(1)65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
(2)前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が、以下のとおりであること
○昭和31年4月2日以後生まれの方…809,000円以下
○昭和31年4月1日以前生まれの方…806,700円以下
(3)同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
給付額(次の(1)と(2)の合計額が支給されます)
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,450円×保険料納付済期間(月数)/480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,551円※×保険料免除期間(月数)/480月
※ 毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
昭和31年4月2日以後生まれの方…保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間は11,551円、保険料1/4免除期間は5,775円
昭和31年4月1日以前生まれの方…保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間は11,518円、保険料1/4免除期間は5,759円
補足的老齢年金生活者支援給付金
老齢年金生活者支援給付金の所得要件(上記支給要件の(2))を満たさない場合であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が以下の方に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する方と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付が支給されます。
○昭和31年4月2日以後生まれの方…809,000円を超え909,000円以下
○昭和31年4月1日以前生まれの方…806,700円を超え906,700円以下
※補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減します。
障害年金生活者支援給付金
支給要件(以下の全てを満たす方)
(1)障害基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得※1が、4,794,000円以下※2であること
※1 障害年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
給付額
障害等級1級 6,813円(月額)
障害等級2級 5,450円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
支給要件(以下の全てを満たす方)
(1)遺族基礎年金の受給者であること
(2)前年の所得※1が、4,794,000円以下※2であること
※1 遺族年金などの非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族等の数に応じて増額
給付額
5,450円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
請求手続き
年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
支給要件に該当しない場合は支給されません。
(1) 新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
お受け取りの対象になる方には、日本年金機構から令和7年9月頃から順次、請求可能な旨のお知らせを送付する予定です。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、切手を貼付して返送してください。
※案内が届いていない場合でも、世帯構成の変更や税額の更正などがあった場合で、支給要件を満たした方は受給できる可能性があるため、お問い合わせください。
(2) 老齢・障害・遺族基礎年金の請求をする方
老齢・障害・遺族基礎年金の請求手続きとあわせて、年金生活者支援給付金についても請求書を提出していただきます。
年金生活者支援給付金を受け取っている方で引き続き支給要件を満たしている場合、翌年以降のお手続きは原則不要です。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより、一度年金生活者支援給付金を受け取れなくなった方が、その後、再び支給要件を満たしたことにより年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。
お問い合わせ先
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216
【受付時間】
月曜日 8時30分~19時
火曜日~金曜日 8時30分~17時15分
第2土曜日 9時30分~16時
※月曜日が祝日の場合、翌開所日は19時まで。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
制度の詳細については、下記リンク先をご参照ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
日本年金機構ホームページ<外部リンク>