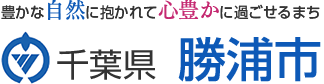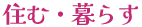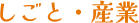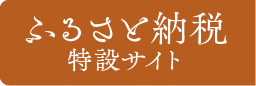本文
特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」にご注意ください
更新日:2025年7月9日更新
印刷ページ表示
クビアカツヤカミキリとは
サクラやモモ、ウメ、スモモなどのバラ科樹木に寄生し、幼虫が樹の内部を食べて枯らしてしまう外来のカミキリムシです。
日本では2012年に愛知県で最初の被害が確認されましたが、国内各地でサクラ並木や果樹園などに大きな被害をもたらしており、2018年1月に「特定外来生物」に指定されました。
日本では2012年に愛知県で最初の被害が確認されましたが、国内各地でサクラ並木や果樹園などに大きな被害をもたらしており、2018年1月に「特定外来生物」に指定されました。
形態
成虫の体長は25-40mm程度。
成虫の前胸背板は明赤色で、他は光沢のある黒色。前胸背板の側面に頑丈なとげ状の瘤(こぶ)を一対持つ(図1及び図2の青矢印の部分)。
触角は黒色で、オス(図1)の触角は体長より長く、メス(図2)の触角は体長と同等か、やや短い。
成虫の前胸背板は明赤色で、他は光沢のある黒色。前胸背板の側面に頑丈なとげ状の瘤(こぶ)を一対持つ(図1及び図2の青矢印の部分)。
触角は黒色で、オス(図1)の触角は体長より長く、メス(図2)の触角は体長と同等か、やや短い。


図1 オス 図2 メス
(写真提供:埼玉県環境科学国際センター)
クビアカツヤカミキリを見つけたら
もしクビアカツヤカミキリを見つけたら、逃がさずにその場で捕殺し、勝浦市生活環境課(環境保全係)か千葉県自然保護課生物多様性センター(043-265-3601)までご連絡下さい。
※特定外来生物である本種を捕まえて、生きたまま持ち帰ることは、法律で禁止されているため、できません。飼育することや販売することなども違法です。これらの規則に対する違反には罰則が設けられています。
※特定外来生物である本種を捕まえて、生きたまま持ち帰ることは、法律で禁止されているため、できません。飼育することや販売することなども違法です。これらの規則に対する違反には罰則が設けられています。
クビアカツヤカミキリ被害の見つけ方
フラス
幼虫の活動期は4月から10月頃までで、この期間の幼虫は、「フラス」と呼ばれる食べた木屑と糞が混ざったものを、幹や枝に開けた孔(排糞孔)から盛んに排出します。
樹皮の表面や枝の分かれ目、根元などでこのフラスを見つけることが、本種の侵入を発見する重要な手掛かりになります。被害を放置してしまうと樹木がダメージを受けてやがて枯死するだけでなく、周辺への被害拡散の供給源にもなってしまいます。
樹皮の表面や枝の分かれ目、根元などでこのフラスを見つけることが、本種の侵入を発見する重要な手掛かりになります。被害を放置してしまうと樹木がダメージを受けてやがて枯死するだけでなく、周辺への被害拡散の供給源にもなってしまいます。


クビアカツヤカミキリのフラス サクラの根元に散乱したフラス
(写真提供:埼玉県環境科学国際センター)
脱出孔
羽化した成虫が樹の外へ出る時に使用した孔で、長径2~3センチ程度、縦長の楕円形です。
また、脱出予定孔(成虫が出る前の樹皮を薄く残した孔)を見つけることで、拡散を未然に防ぐことができます。
また、脱出予定孔(成虫が出る前の樹皮を薄く残した孔)を見つけることで、拡散を未然に防ぐことができます。

成虫脱出孔
(写真提供:埼玉県環境科学国際センター)
関連リンク
環境省<外部リンク>
国立研究開発法人 森林研究・整備機構<外部リンク>