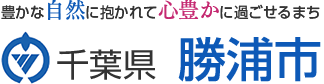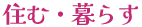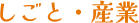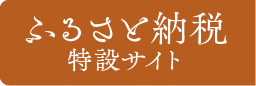本文
国民健康保険 保険税の軽減
世帯の前年の所得が下記の基準額の世帯については、均等割額及び平等割額について減額されます。
保険税の軽減について
世帯の前年の所得が下記の基準額の世帯については、均等割額及び平等割額について減額されます。
| 世帯全体の総所得および山林所得の合計が43万円+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 | 7割軽減 |
|---|---|
| 世帯全体の総所得および山林所得の合計が43万円+30.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 | 5割軽減 |
| 世帯全体の総所得および山林所得の合計が43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者(※2)の数)+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の世帯 | 2割軽減 |
(※1)給与所得者等とは、世帯内の世帯主並びに被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、給与収入(専従者給与を除く)55万円超もしくは公的年金等の収入が125万円(65歳未満は60万円)を超える人のことです。
(※2)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、引き続き同じ世帯に属する人のことです。65歳以上の人の公的年金に係る所得については、その所得から15万円を控除した金額で判定します。
軽減を受けるためには、住民税の申告書を提出する必要があります。
無収入の方、非課税となる遺族年金・障害者年金等を受給されている方など、確定申告・市県民税の申告が必要でない方でも、軽減を受けるためには申告が必要です。
後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置について
後期高齢者医療制度の創設に伴い、75歳以上の方(65歳以上の方で一定の障害がある方を含む)が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したために、保険税の負担が増えないような措置が講じられています。
1.世帯内で75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入している場合
- 保険税の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を受けていた世帯については、引き続き軽減が受けられるように、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより国民健康保険の被保険者でなくなった方も含めて軽減を判定します。
- 国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことにより、国保の被保険者が1人になった場合は、医療分及び支援分の平等割額が5年間半額になり、その後3年間は4分の1減額されます。
※ 措置を受けるための申請は必要ありませんが、世帯主等に異動があった場合は適用されなくなります。
2.保険料負担のなかった65歳以上の被用者保険の被扶養者(以下、「旧被扶養者」)が、被用者保険の被保険者の後期高齢者医療制度加入に伴い、国民健康保険に加入した場合(7割・5割の軽減該当の場合を除く)
- 所得割額が全額免除に、1人あたりにかかる均等割額が半額となります。
- 被扶養者だった方のみが国民健康保険に加入する世帯の場合は、さらに1世帯あたりにかかる平等割額も半額になります。
平成31(令和元)年度以降の旧被扶養者減免に係る一部見直しについて
平成31年4月1日より旧被扶養者に係る減免制度が見直され、均等割額及び平等割額の減免期間が「当分の間」から「国保に加入した月から2年間」に変更となりました。これは、平成30年度以前に加入した旧被扶養者にも適用されます。なお、所得割額の減免は当分の間継続されます。
※ 申請が必要となりますので該当する方は申請をお願いします。
被保険者である未就学児の均等割額の軽減について
未就学児の均等割額(7割・5割・2割の所得軽減適用世帯は軽減後の均等割額)を2分の1軽減します。
| 所得軽減 適用世帯 |
未就学児の均等割額 ※()内は軽減割合 | |
|---|---|---|
| 軽減適用前 | 軽減適用後 | |
| 7割軽減世帯 | 11,880円(7割) | 5,940円(8.5割) |
| 5割軽減世帯 | 19,800円(5割) | 9,900円(7.5割) |
| 2割軽減世帯 | 31,680円(2割) | 15,840円(6割) |
| 軽減なし世帯 | 39,600円(軽減なし) | 19,800円(5割) |
※保険税は課税区分ごとに合算後100円未満の端数切捨てとなります。
※未就学児に係る減額を受けるための申請は不要ですが、所得軽減は未申告世帯に対して適用されないため、所得の申告をお願いします。