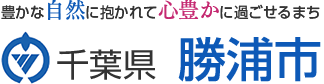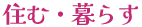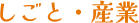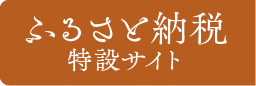本文
後期高齢者医療保険料
後期高齢者制度の保険料は、被保険者(75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があると認められた方)一人ひとりに負担して頂きます。原則として、県内均一の保険料率が定められており、2年ごとに見直しを行います。
ページ内リンク
保険料の決め方
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して個人ごとに計算されます。
保険料額の計算(令和7年度)
年間保険料額=(1)均等割額+(2)所得割額
(上限は80万円。100円未満の保険料切り捨て)
(1)均等割額 43,800円
(2)所得割額(前年の総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.11%
年度の途中で75歳の誕生日を迎えた方や本市に転入した方(資格取得者)は、その月から月割で計算します。
保険料額の軽減措置
所得の低い方の均等割額の軽減
世帯の所得水準に応じて下表のとおり軽減されます。
| 軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1※)以下の場合 | 7割 | 13,140円/年 |
| 43万円+(30.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1※)以下の場合 | 5割 | 21,900円/年 |
| 43万円+(56万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数-1※)以下の場合 | 2割 | 35,040円/年 |
※ 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
均等割額の軽減を判定する際の注意事項
- 65歳以上(1月1日時点)の方は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。
- 判定の基準日は毎年4月1日です。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日となります。)
- 専従者控除を受けている場合は、専従者控除前の金額で判定します。
(専従者給与を受け取っている場合は、専従者給与は判定の対象になりません。) - 土地譲渡所得等の特別控除がある場合、特別控除前の金額で判定します。
(所得割額計算の際は土地譲渡所得等の特別控除後の金額で算定します。)
被用者保険の被扶養者であった方の保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、均等割額は加入後2年間のみ5割軽減されます。(国民健康保険および国民健康保険組合に加入されていた方は対象になりません。)
保険料の試算
以下のホームページで後期高齢者医療制度に加入した場合の保険料額を試算できます。
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料の試算)<外部リンク>
保険料の納め方
保険料は、原則として公的年金からの天引きとなります。(特別徴収)
特別徴収とならない方(※1)は納付書や口座振替により納付していただきます。(普通徴収)
毎年7月中旬に市からお送りする保険料額決定通知書等をご確認ください。保険料が年金天引きとならず、口座振替の申し込みをしていない場合(※2)、各期別の納付書が当該年度分まとめて同封されています。
※1 特別徴収とならない場合
- 年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料と合わせた保険料額が、特別徴収対象の年金額の1/2を超える方
- 当該年度途中で75歳になった方や65歳以上で一定の障害の認定を受けた方
- 当該年度途中で他の区市町村から転入した方
※2 保険料の口座振替について
75歳になるまで国民健康保険税を口座振替で納付されていた方は、後期高齢者医療保険料に移行された時は口座情報は引き継げませんので、改めてお申込みが必要となります。口座振替を希望される場合は市役所税務課窓口または取扱金融機関窓口へお申し込み下さい。
特別徴収を口座振替(普通徴収)に変更できます
保険料を年金天引きにより納付している方は、申し出により口座振替による納付に切り替えることがきます。預金通帳と通帳印をご持参のうえ、市役所税務課へお申し出ください。口座振替のお申込みとともに、「後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書」の提出が必要です。
保険料の納付が困難な場合はご相談ください
災害等により重大な損害を受けた時や事業の休廃止等により収入が著しく減少した事により保険料を納めることが困難になった時は、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
災害などの特別な事情がなく、保険料を滞納した時は療養費や高額療養費などの保険給付の全部または一部を差し止め、その給付分を滞納保険料に充てることがあります。また、財産の差し押さえなど滞納処分を受けることもあります。
保険料は、収入が少ない人に負担が大きくならないように保険料額を設定しています。納付期限内に納付が困難な場合は分割納付などの相談をお受けします。
【保険料について問い合わせ】
税務課課税係(賦課について Tel:0470-73-6623)
税務課収納係(口座振替・納付相談について Tel:0470-73-6622)
千葉県後期高齢者医療広域連合(Tel:043-308-6768)
関連リンク
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>